アウェアファイではAIの活用の場面として、「ユーザー向け」と「自社向け」とがあります。「ユーザー向け」については、プロダクトとしてのアウェアファイの中に、どのようにAIの機能を組み込み価値を創出するか、という関心事になります。「自社向け」については、広い意味での「生産性向上」ということになると思います。
今回、そんな自社向けのなかでも、特にプロダクト開発に携わるエンジニアがユーザーとなるAIの利用、という観点で、アウェアファイが活用しているAI、活用できていないAI、活用しようとしているAIをざっと紹介しようと思います。
全社またはチーム導入しているAI
GitHub Copilot
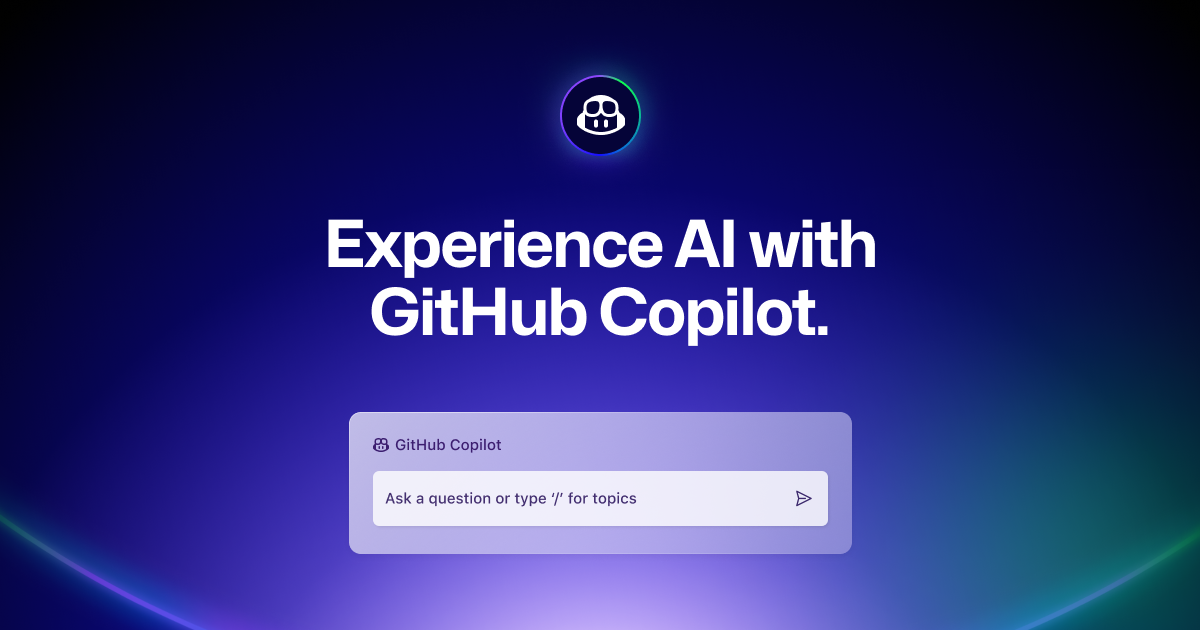
GitHub Copilotがのチーム向けプランがリリースされたのは2023年2月のことですが、当月中に全エンジニア向けの導入を決め、以来活用を続けています。
Eraser

Eraserは、ソフトウェアやシステムの設計におけるダイアグラムを記述・描画することに特化したSaaSです。クラス図やシーケンス図などの記述にMermaid記法が用いられることが多いと思います。Eraserで扱うのはMermaid記法ではなく独自の記法ではあるのですが、AIによる生成や補完に対応しているので、学習コストが高くない印象です。
アウェアファイでは、機能の実装前にモデリングを実施して設計のすり合わせを行うのですが、その際にEraserを使って作図するようにしています。
Qodo
PR-Agentという名前に馴染みのあるかたもいるかも知れません。Qodo(たぶんコードと読む)は、PR-AgentのSaaS版です。

アカウント、リポジトリを連携して設定ファイルをYAMLで書いておけば、pull-requestにまつわるさまざまな作業をAIが行ってくれます。例えば次のようなタスクが含まれます。
- コミットメッセージの作成
- コードレビュー
- pull-requestの内容を判別し、タイトルや概要文の自動生成
レビュー観点や社内のコーディング規約をプロンプトに追加することもできるので、育てていけばより機能しそうな気がしています。
タイトルや概要文の生成については、pull-requestの粒度の適切さに依存する前提ではありますが、人間が雑に書くよりはいいものが生成される、という感触です(ちなみに英語のまま運用しています)。
ChatGPT
アウェアファイではエンジニア職か否かを問わずChatGPTのTeamプランを全社導入しています。
必要最小限の運用ポリシーを定め、あとの利用は各自の判断として全社導入を決め運用しています。
試験導入・一部導入しているAI
Perplexity
Perplexityは、Web検索に特化したAIエージェントサービスです。
Perplexityはサービス比較のために個人的に導入していた時期がありました。ごく最近、Perplexity hostedなDeepSeekが利用できるようになっていたりもします。後述のFeloや、ごく最近発表された OpenAI Deep Research とかなり直接的な競合になることが予想されるので動向が気になります。
Felo

Perplexityと同じカテゴリーの、検索に特化したAIエージェントサービスです。検索結果からスライドを作成したり、マインドマップを展開したりと、Perplexityと機能面や使い勝手の面で違いがあります。
Feloは池内のほか、研究を主幹しているメンバーが利用しています。
僕自身はPerplexityやFeloを使い慣れていて、Google検索をすることは誇張抜きにほとんどなくなりました。
Devin

ソフトウェア開発のためのAIエージェントです。Co-pilot的なAIコーディングアシスタントは多くのサービスがローンチされていると思いますが、Devinはあたかもひとりのエンジニアをチームに向かい入れるかのような体験を提供している点がユニークです。
2025年に入り、アウェアファイSlack内に #onboarding-devin チャンネルをつくってオンボーディングをするなど、AIとのコラボレーションを進めようとしています。
Dify
DifyはAIエージェントをGUIで構築できる、AIエージェントビルダーです。

アウェアファイのプロダクトでは、AIエージェントの構築にはDifyは利用しておらず、プロトタイピングやプロンプトの検証用途で一部メンバーが利用しています。
ひとりひとりがDifyを利用して業務改善のためのエージェントを構築できるような水準になっていると、企業のAIx = AIトランスフォーメーションの浸透度としては高いと言えるのではないでしょうか。アウェアファイではまだ途上ですが、Difyのヘビーユーザーが心理職だったりなどし、あらたなプラクティスの息吹を感じています。
cline
clineは、VSCodeの拡張機能として動作するAIコーディングエージェントです。
clineのAI APIの利用先としてはClaudeに限らないのですが、出発点としてはAnthropic の Computer Use活用することを最大の強みとしていて、ファイル作成やテスト実行、デバッグ、修正などの開発業務を自動で進めてくれます。
Devinが開発タスクの非同期的な依頼だとすると、clineは同期的なペアプロに近い感覚です。
Cursor
Cursorも説明不要かと思います。本稿で掲載したAIツールと比較して、使い分けや評価が十分ではない状態なので、チーム導入には至っていません。
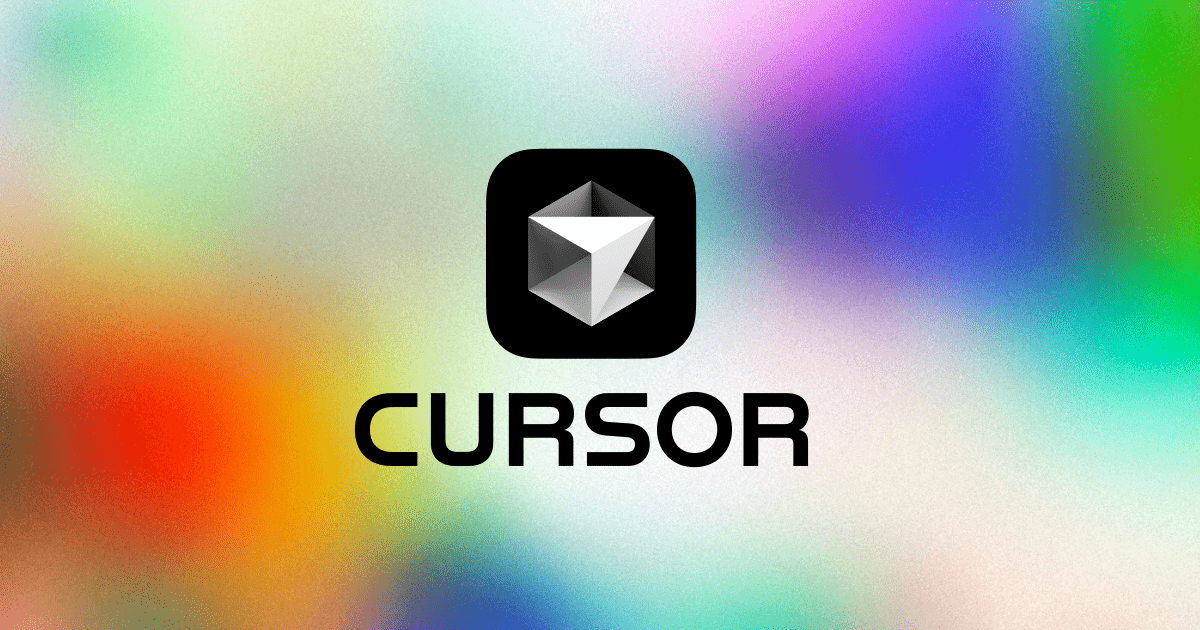
Windsurf
WindsurfはCursorのような、AI時代のコードエディターです。

WindsurfはCursorと比べ、プロジェクト(ディレクトリ)全体のコンテクスト理解に強い、複数ファイルにまたがった編集に強いという評価をされることが多いようです。正確には、そのように振る舞うよう初期設定が寄せられているということかも知れません。CursorとWindsurfのどちらかをチーム導入しようかと検討しているところです。
WindsurfとCursorについて、Feloに聞いた比較記事を置いておきます。

Claude

アウェアファイのプロダクトではAnthropic提供のAIモデルであるClaude Sonnetは本格的に活用しているのですが、チャットGUIとしてのClaudeはChatGPTの住み分け問題もあり部分導入にとどまっています。clineのAPI利用先としては開放されていたりもしますね。
個人的に導入しているAI
ChatGPT Pro
全社導入するには流石に費用対効果が気になるレベルなので、こっそり使っています。今日はDeep Researchを試していました。
Gemini Advanced
GoogleのAIです。GeminiにもDeep Researchという同名の機能(ちなみにGeminiのほうが先にリリースしています)が搭載されているのですが、個人プランにしか提供されていないようだったので契約して利用してみていました。OpenAIのDeep Researchがリリースされたことで、Geminiは解約することになりました...。
導入していないが気になっているAI
UIデザイン〜UI開発プロセスをAIによってどのように進化させるかということが最近の関心事です。逆にいうと、AIの導入が進んでいない部分でもあります。気になっているもの、比較選定している段階のものを列挙します。
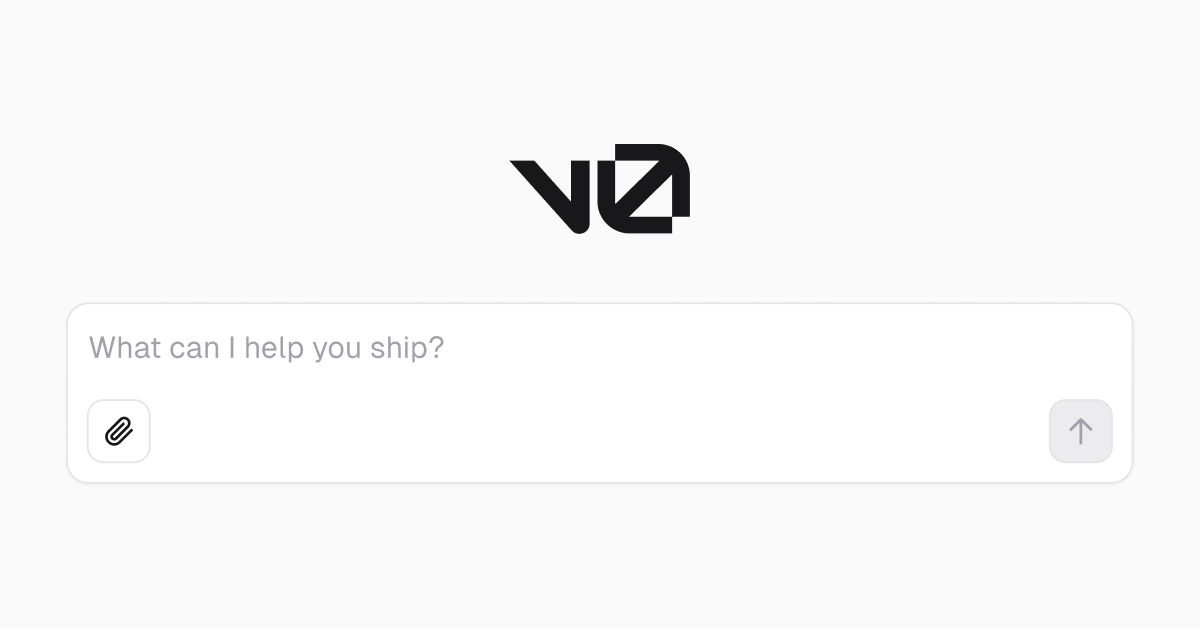
v0はAIによるUI生成で有力候補になるツールだと思います。Next.jsのアクティブなプロダクトがなく導入の動機が強くないことから導入に至っていません。厳密にフレームワークにしばりがあるわけではなさそうなので、挑戦したいツールではあります。

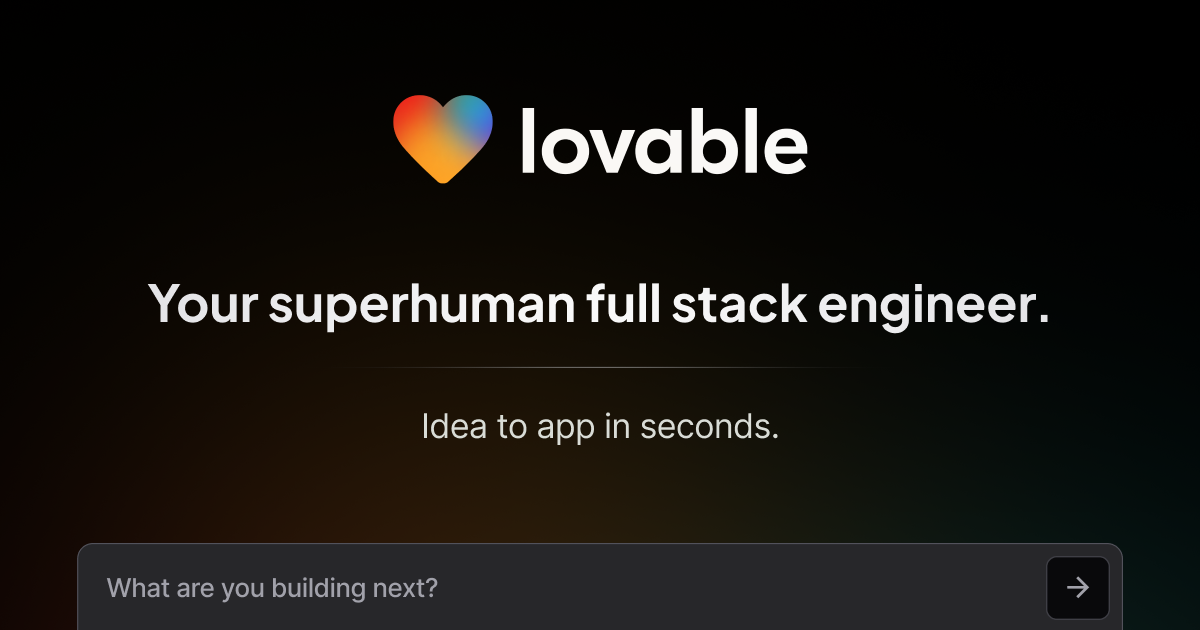
Replit、LovableはどちらもWebアプリをテキストから生成し、デプロイまでワンストップで行うサービスです。ゼロベースでプロダクトやプロトタイプを立ち上げるタイミングではないことから、導入には至っていません。エンジニアチーム以外でむしろ導入が進む、などの動きができるとむしろ面白いなと感じる領域です。
おわりに
昨年、2024年からAI活用のユースケースが洗練されてきたのか、毎週のように新しいAI Poweredなサービスがローンチされている状況です。そんななかでさまざまなツールを検証するのは楽しいいっぽう、プロダクトの資産を管理する基幹部分を担ってもらうには、安定性や継続性が重要であるという観点は忘れてはならない点です。生成からデプロイまで一気通貫で行えるサービスがあるとして、運用面での課題はないのか、サービス自体の継続性はあるのか、といったことは未知数な部分が大きく、"実験的に"利用せざるを得ない状況がしばらく続くのではないかと思います。
とはいえ、日常的にAIとコラボレーションする働き方がこれから前提となっていくなか、AIとの相互理解を進める意味でも日々実験を繰り返していくことが大切だと感じています。
アウェアファイでは、AIにエンパワメントされながらユーザーの人生を豊かにするためのプロダクト開発をするという体験が得られる環境です。少しでも興味をお持ちいただけましたら、 @iktakahiro へ気軽にお声掛けいただくか、問い合わせフォームよりご連絡ください。お待ちしています。


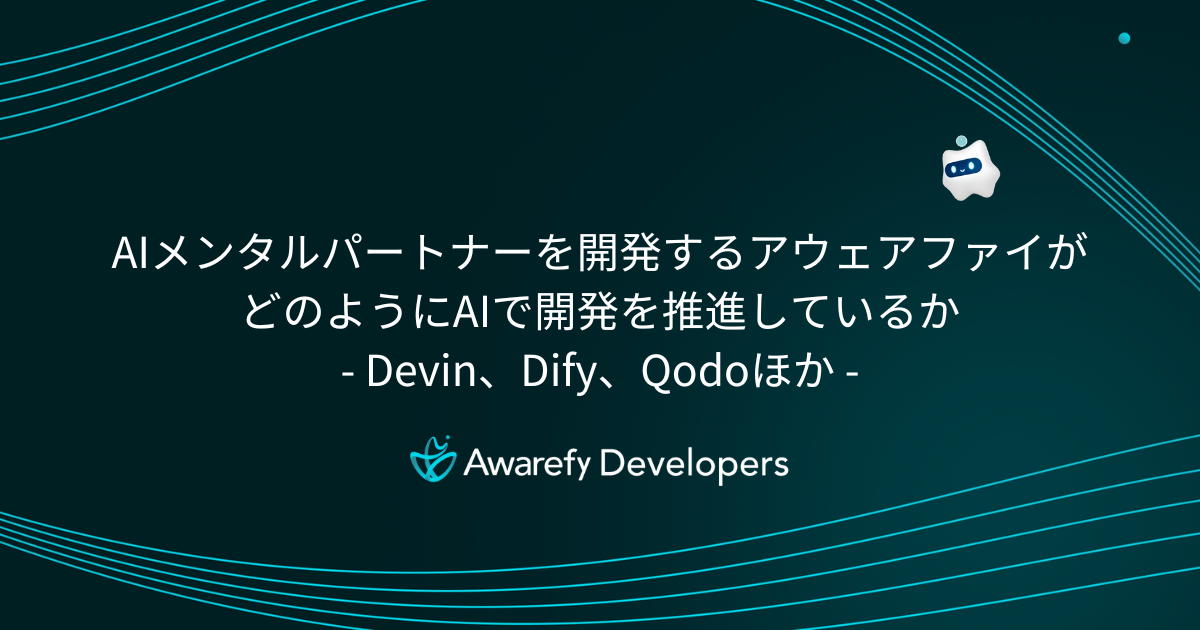


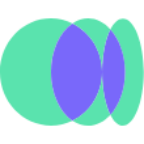


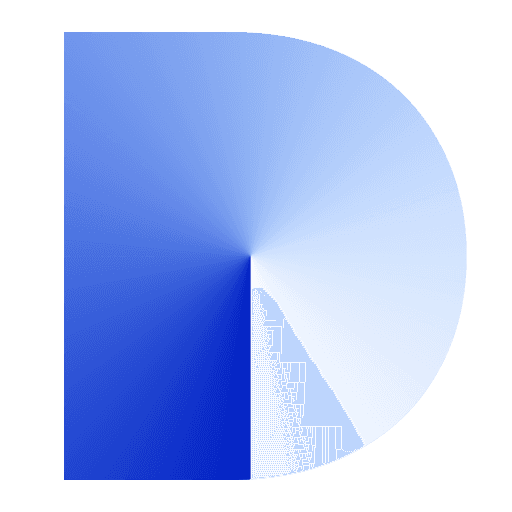




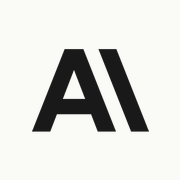

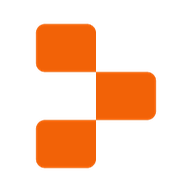
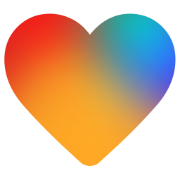

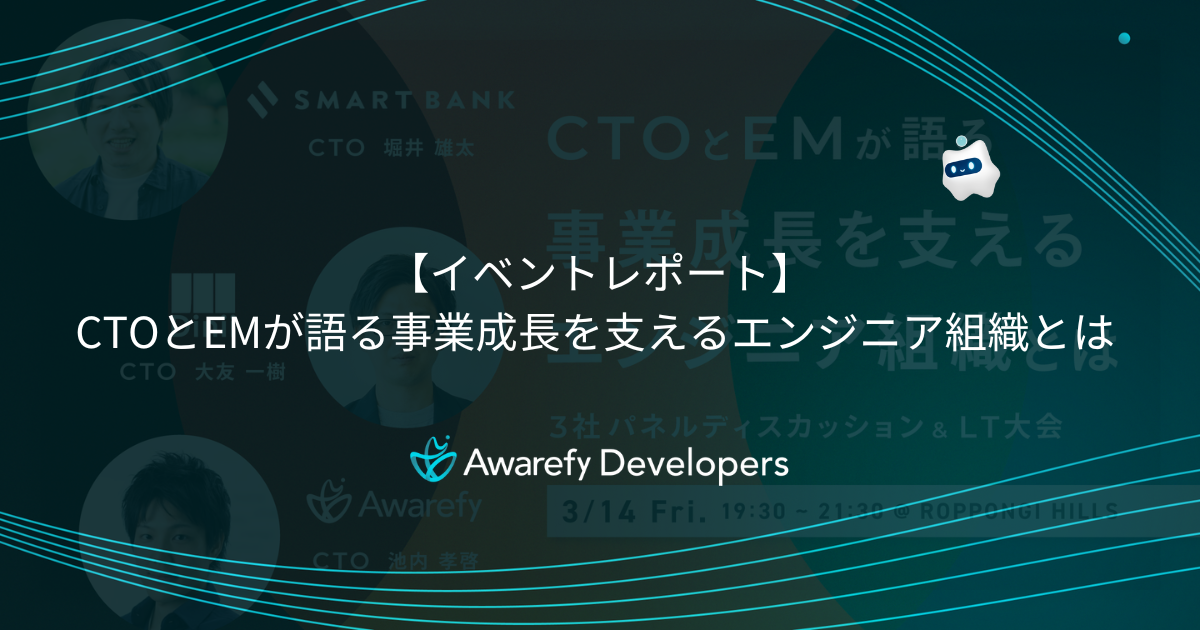


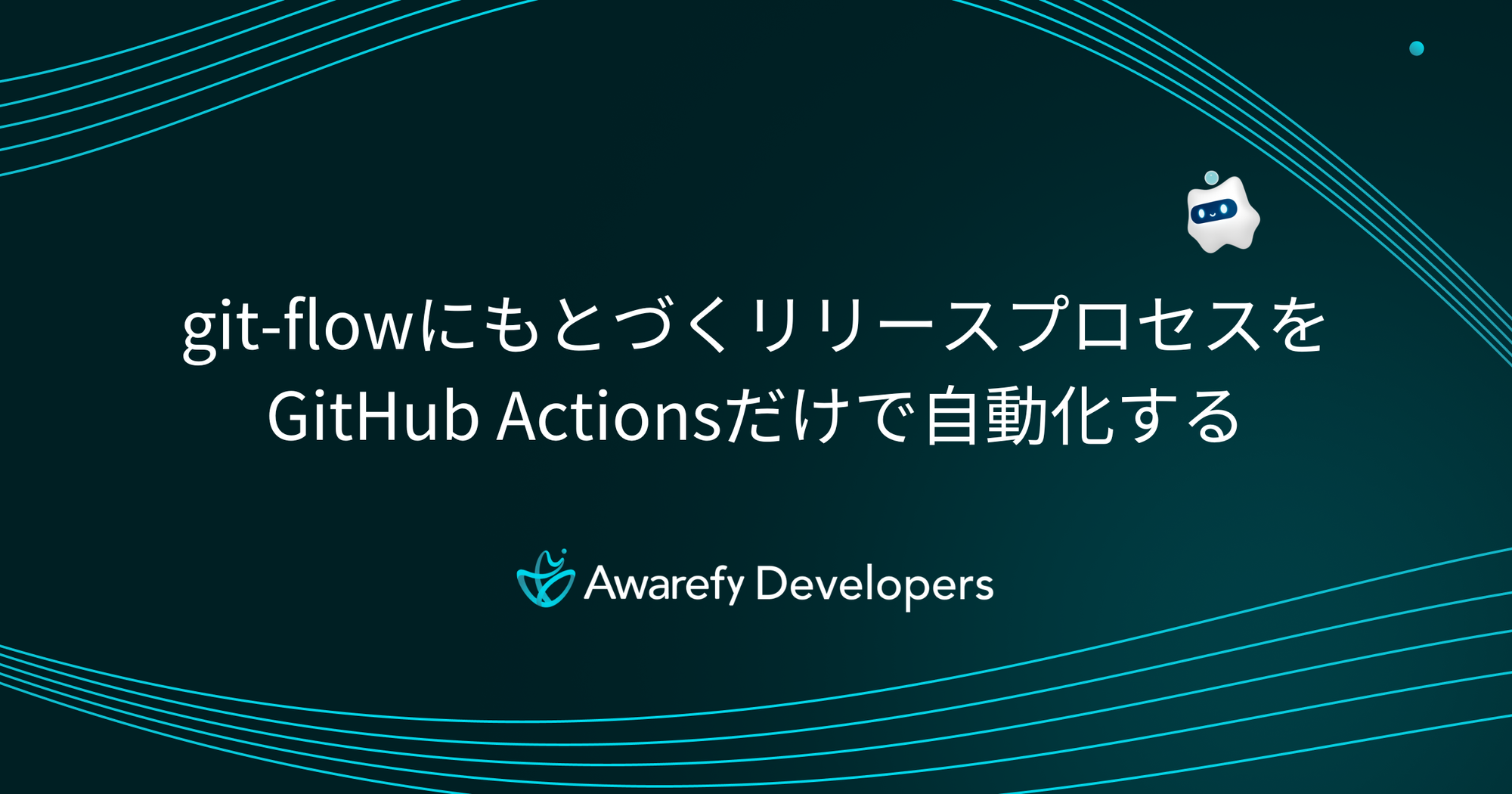
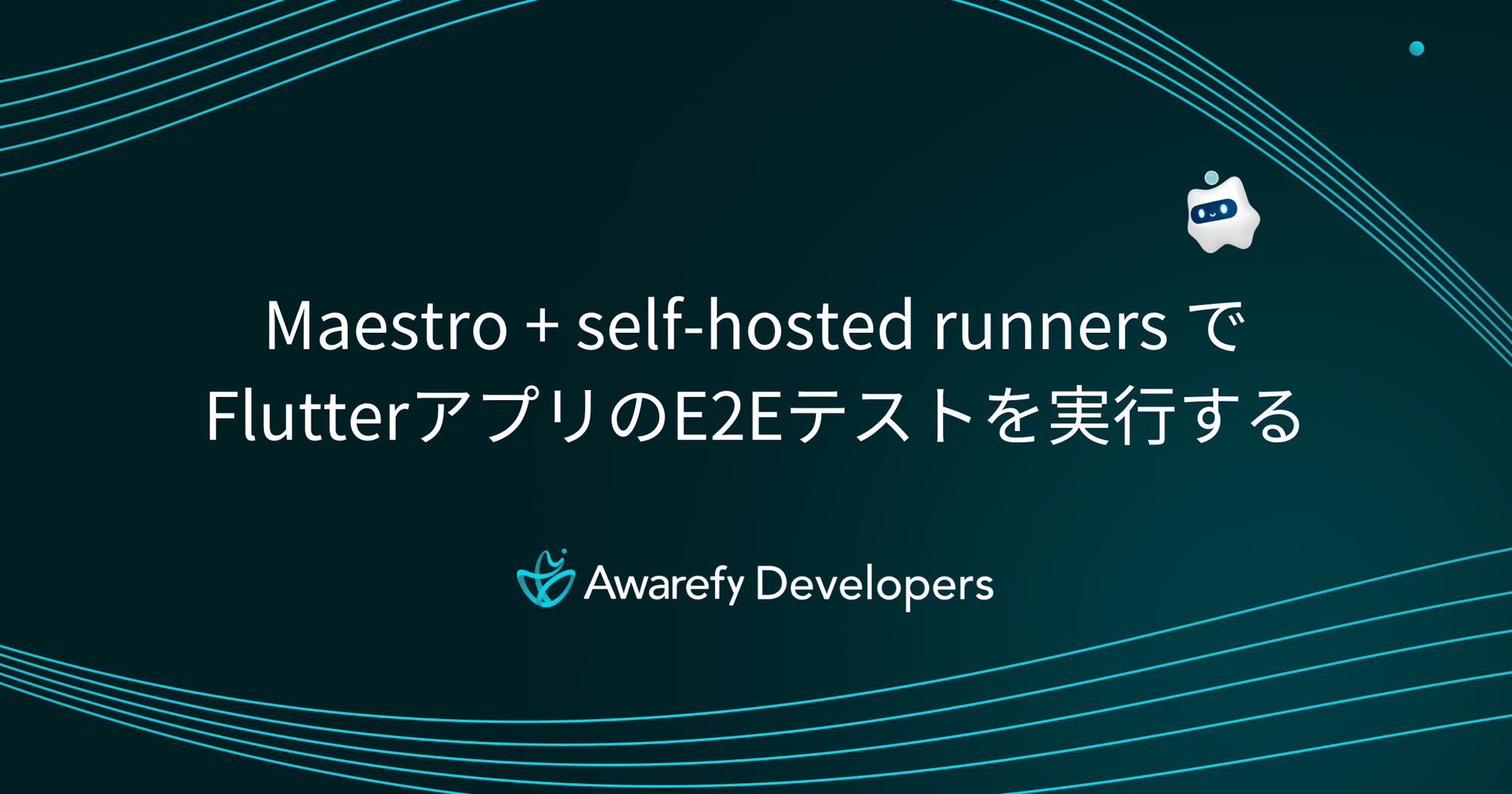



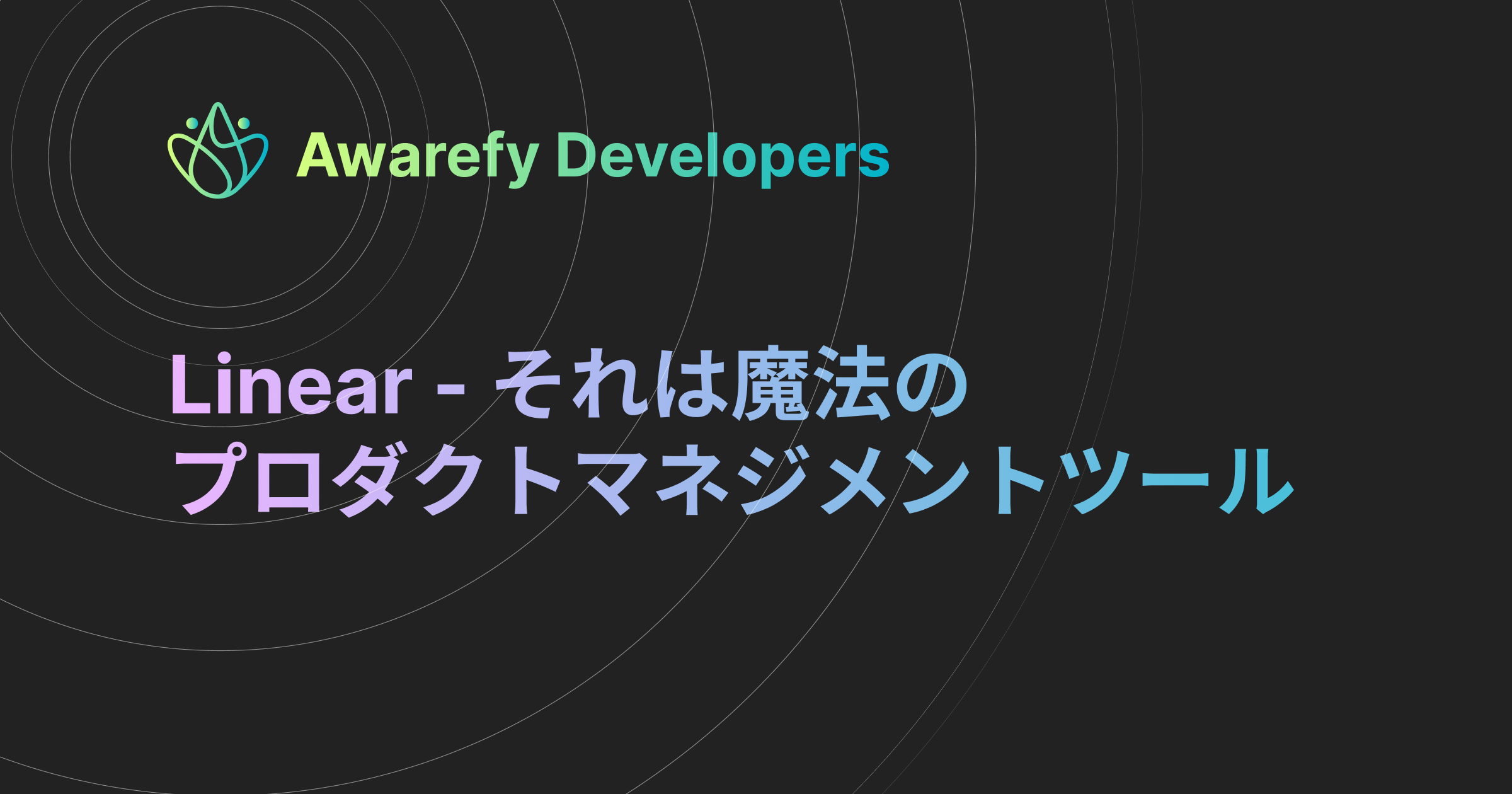



Discussion